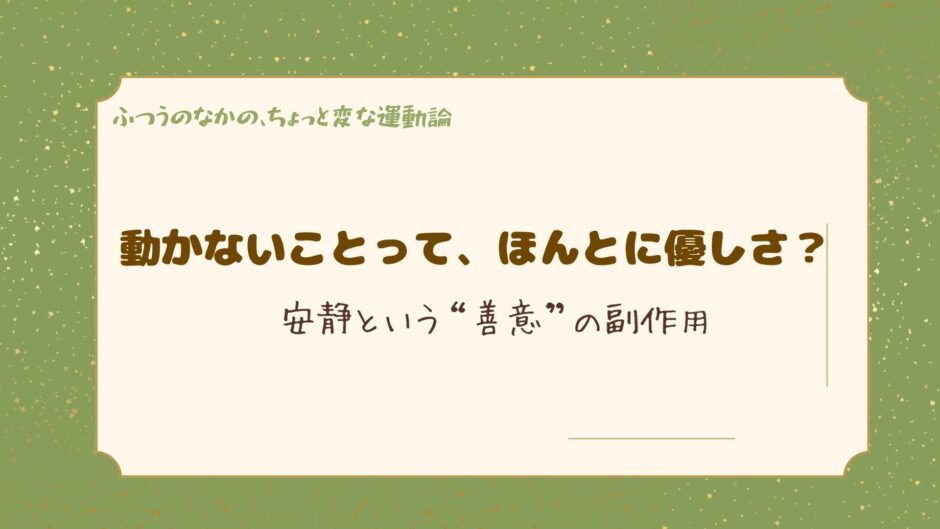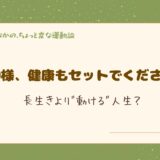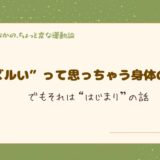自分の身体が、“サボり癖”を覚える瞬間
目次
①サボリ癖って、身体にもあるんだ
一度さぼり癖がついた自分。
なかなか戻ってこない。
何なら「まだ無理っす」って言い訳ばっか繰り返してる。
──身体も、けっこう似てる。
休みが必要、でも「ずっと休む」はちょっと違うみたい
ケガで痛くなったらどうする?
そらもう年末年始スタート気分で安静第一でしょ。
でもね。ケガや痛みであっても休む適量ってのがあるみたいなんだ。
サボリ癖がつきすぎてる私。
もうどっちが私だか、”サボリ”だか見分けがつかないレベル。
でもそんな私でも……
どんな人格者だろうと共通することがある。
休みすぎは身体に良くないってこと。
……いや、ウソでしょ。
どこぞのワーカホリック理論だよ。
って思うよね。
でもそうも言ってられない事情もあるみたい。
「動かなかった人たち」のその後
実際、腰痛患者が“どれくらい休んだか”と“その後どうなったか”を調べた研究があるんだ。
それによると、【休みすぎは延々と続く痛みのリスクファクターになる】って指摘されてるんだ。
…….リスクファクター?
横文字を並べて権威に浸ってるわけじゃないよ。
日本語だと”危険因子”って呼ぶみたい。
いわゆるトラブルを持ってくる”問題児”のこと。
“休みすぎ’は【痛みをつれてくる問題児】なんだって。
痛くても休んでよい期間は?
しかも期間はというと……。
研究によっては4日以上休むとダメだったって報告もあったりする。
いやいや、バカなの?
痛いときでもゴールデンウィーク未満しか休ませてくれないの?
……うん、そうみたい。現実は厳しいな。
他の研究にもそういう類のがけっこう沢山あるんだ。
そんな休むことを否定するような研究しないでよって感じだけど。
ギプスで固定した末路
例えば、元気な人の腕をギプスで固定した研究がある。
別にイタズラじゃないよ。
元気な人でも動かないようにしたらどうなるのかなっていう研究。
それも4週間……。
そんなの勘弁。
私なら最初こそは、ギプスをパンチンググローブに見立てて楽しむだろう。
でも、多分4分もしたら飽きる自信がある。
その後は「もうはずさせて」ってなる。
それを4週間固定なんて…。
「もし私が千手観音だったら…」って。
いや、それでも私はギプスはごめんこうむりたいって思うのかもな。
何百本、何千本あっても私の腕はやらん…ってなりそう。
だがら実際に固定した人は勇者だと思う。
で、その勇者たちの結果はどうだったと思う?
半数は冷たいって感覚が悪く、3割以上は熱さの感覚が悪くなったんだって。
痛みにも敏感になったらしい。
……何だそれ。良いことなしだな。
その通り。”過度な安静”って良いことないんだよね。
②痛みに敏感なカラダ、つくってない?
実際に固定期間が長い人ほど回復まで時間がかかった。
さらに延々と続く痛み状態に繋がるリスクが高かったみたい。
何でもかんでも動いたら良い……って答えを求めないで
じゃあ、動かしたら良いの?って思うよね。
うん、方向性としては合ってる。
たいていの場合、それで合ってるんだよ。
けど諸々と条件がついてくることもある。
そんなこと言われたらなんでってなるけど。
言い切ってよ。
答えが欲しいのにって。
でも、これは
お肉は嫌いだけどハンバーグは好き。
玉ねぎは嫌いだけどタルタルソースは好き。
みたいなものかもしれない。
嫌いで絶対受け付けないものが入っていても条件が違えば食べれるってのと同じ……ではないんだけど。
“好き”、”嫌い”と同じで、”正しい”と”間違い”にも二者択一にならないことって沢山あると思ってる。
そんなイメージを持ってくれると良いな。あくまでもイメージ。
こればっかりは状況によるところはあるんだよね。
それが難しいところ。
言い切れない理由がそこにあるんだ。
凄いもどかしいけどね。
0-100思考には注意
医療の世界にもグラデーションがあるんだ。
だからここは無責任には言い切れないところなんだ。
私もいちおう医療現場にいるからね。
ただ、ここで1つ豆知識を紹介するね。
比較的最近の話で、注目されてる考えがあるんだ。
最後にちょっとだけ、その話もしてみようかな。
③”うごくこと”が、痛みをやわらげる?──EIHっていう現象
動くこと、つまり運動には痛みを和らげる効果があるみたい。
EIHの由来は?
運動、引き起こす、痛覚鈍麻。
この3つの英語の頭文字をとってEIHって言うんだ。
(Exercise-Induced Hypoalgesia)
関係ないけど公文にもEIHってあるみたい。
こっちはEnglish Immersion Hourの略で文字通り、英語にどっぷりひたるみたい。
楽しそうだな。
子どもの時に公文に通ってたことあるけど、昔はこんなのなかったな。
そっちも魅力的だけど、今日は運動の方のEIH。
これは運動自体に痛みを和らげる働きがあるってことみたい。
これこそワーカホリック理論?、根性論?って思ってしまうよね?
けどホントみたい。
メカニズム自体はまだちゃんと解明されてるわけじゃないけど実際にあるみたい。
メカニズムは知らなくても、効くものは効いちゃう。
EIHのメカニズム
ん、なに?
わかってる段階でメカニズムが知りたいって?
聞いて後悔しないかな?
気になる人のためにも、あくまでも仮説だけど載せとくよ。
メカニズムの仮説はこんなの。
↓
- オピオイドやノルアドレナリン、セロトニン、エンドカンナビノイドが関与して内因性疼痛抑制システムを作動させる。
- 運動によって産生される一酸化窒素によってNO/cGMP/K+ATP pathwayを介して疼痛を抑制する。
- 運動によって末梢の免疫系に変化が生じる。
(引用:下和弘.慢性疼痛に対する運動療法の最近のエビデンス,MB Med Reha No.242)
どうかな?
私は後悔した。
む..難しい。
いや”難しい”って言葉を使うのもおこがましいな。
私の身(頭)の丈にあってない。
わからなくたって問題ない?
でも大丈夫。
極端なことを言っちゃうと、別にメカニズムって必ずしも完璧に理解することないって私は思ってる。
3割は開き直り、7割は本気。
例えばスマホ。
今や私のプライベートでも、仕事でも、サボリ癖を発揮するにも欠かせない必需品。
けどスマホのメカニズムって私は全くわからない。
スマホの原理とか中身とか、誕生してくる過程すら知らない。
そんな理解を示さない無慈悲な私なのに、スマホは私に尽くしてくれる。
なんでそんなに……。
ってくらいにありがたい。
要はメカニズムまで細かくて知らなくても、それを使ったり活用することはできるんだ。
これは運動でも同じ。
④“気のせい”に気をつけて──理屈と現実のギャップ
ただね、気をつけたいこともあったりする。
気のせい注意報
効果が実際にあるように思えても、世の中には’気のせい”ってのもある。
“気のせい”の力も大切。
それがすごく役にたつこともあるんだけどね。
ただ”良い気のせい”と”悪い気のせい”があるのが厄介。
その中でも”悪い気のせい”には注意しないといけない。
ここだけの話、これは現場にいる専門職でもやっちゃいがちなんだよね。
ダメな”あるある”。
陥りやすい失敗
例えをあげると【理屈が通ってるから意味があるだろう、正しいだろう】って考え……。
ロジカル思考が強い人に起こりがち。
何がダメなのって感じるよね。
これは難しい話なんだけど……。
実はこの考え”だけ”だと、エラーが起こる可能性が高くなるんだ。
理屈は通ってる風でも現実世界はその通りにならないことだって沢山ある。
このことについてはまた別の機会に取り上げたいなって思ってる。
私だって、夜更かしはしないように気をつけてる。
お酒も飲み過ぎには気をつけてる。
でも現実世界ではたまにしてしまう。
ただ、そういうたまにする夜更かしとか深酒が、私にとって至福の時になったりすることもある。
理屈と現実は違うぜ……って。
いや、それはやめなさいって話だけど。
私の自堕落タイムの良し悪しはさておき。
動くことは良いことがいっぱい
ただ、運動することが痛みを和らげるってのは沢山の研究報告があるんだ。
今回の”EIH”っていう専門用語を使わなくても。
びっくりかもしれないけど、痛いところと関係のないとこの筋トレをしても痛みを和らげる効果があったりする。
……なんだその気まぐれ現象は。
向き合わなくても君は応えてくれるのかって。
人のカラダって不思議だよね。
⑤今日の小さな補足。
参考文献
・Verbunt J A,et al:A new episode of low back pain : who relies on bed rest?,Eur J pain, 12:505-516,2008.
→コホート研究(282名の腰痛患者(発症から7週間以内)
・①と②を目的に実施された研究。
①急性疼痛において安静を選択する患者の特徴の有無を調べる。
②疼痛の急性期における長期の安静が長期の障害につながるかどうかを調べる。
本文中では紹介しませんでしたが、過度な安静をとる人の特徴として、破局思考や恐怖心といったことが強く影響している可能性が示唆されました。
痛みの原因や痛みの強さ以上に”心理面”が過度な安静に繋がりやすい可能性が示されたというのは興味深い話ですね。
破局思考って何?
実際以上にネガティブに考えてしまう思考。
過度の心配や”原因が何か”といったことを過剰に考えてしまうような思考。
こういった思考、心理状態は慢性疼痛の原因のひとつとして考えられています。
その他参考文献
・Terkelsen AJ, Bach FW, Jensen TS.. Experimental forearm immobilization in humans induces cold and mechanical hyperalgesia. Anesthesiology 2008;109:297–307.
・Butler SH:Disuse and CRPS.In:Harden RN,etal,Complex Regional Pain Syndrome,Progress in Pain Research and Management 22
・慢性疼痛に対する運動療法の最近のエビデンス,MB Med Reha No.242