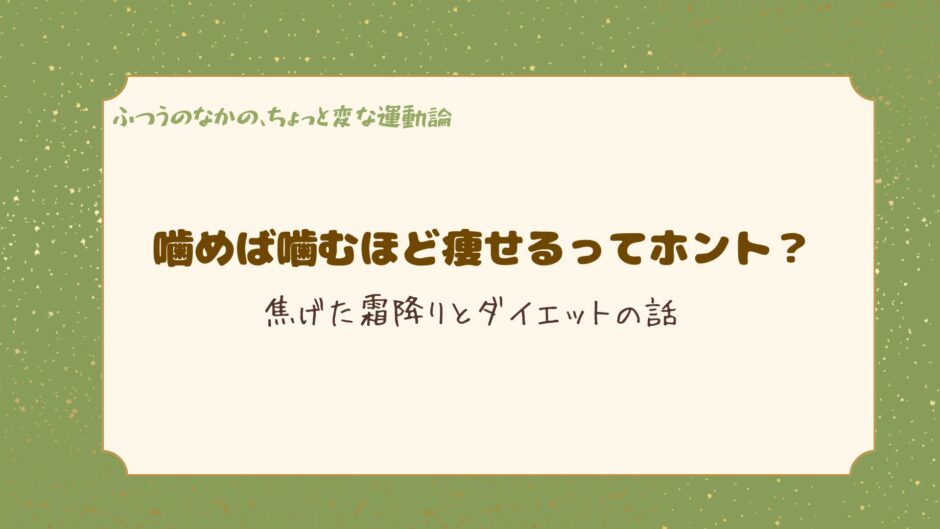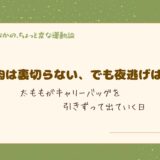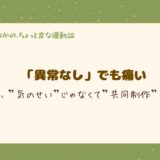私の言葉は全く説得力を持たない
……が、噛むこと”は兵站となり得る
痩せたい人は良く噛め?
目次
①「よく噛むと痩せる」ってホント?
「よく噛むと痩せるらしいよ」
「早食いは太るらしいよ」
そんなことを聞いたことはないかな?
私は良く聞いた。
じゃあガムを噛んでれば痩せられるの?
って期待感と、
「そんなわけなくない?」
っていう猜疑心が喧嘩をする。
そんな噛むことと太る・痩せるの関係について
→アテにならない私の実体験
→ 疑問提起
→ 基本理論の整理
→ 噛む行為のメカニズム
→ まとめ
って感じで書いていきます。
②私の疑いと、ちょっとした実体験から
私は自他共に認める早食いだ。
自覚は乏しいが、食べる早さから逆算すればよく噛んでないことが容易に想像がつく。
けれど私は痩せている。
「カレーは飲み物」なんてフレーズは、私には似合わない。
ただ、痩せ型とはいえ、食べる量の多さに時に驚かれることもある。
加えて私はそれなりの呑んべい。
そのせいで、飲みの席では看護師さんに「あなたの飲んでるお酒にエンシュア(※1)を入れたい」と言われる始末である。
(※1:食事から十分な栄養を摂ることが難しい患者に対して、栄養を補給するために用いられる栄養剤の一種)
元々、太ってたわけではないが痩せたが故に得た経験もある。
ある日、6〜7年ぶりくらいに自転車に乗った時があった。
その時に昔にはなかった決定的な違和感を感じた。
お尻が痛い……。とにかくお尻が痛いのである。
理由は明確だった。
お尻の肉がなさすぎて痛かったである。
平地、段差関係なく全ての振動が何も緩衝せずにダイレクトに伝わってくるのがわかった。
まさにお尻をどつかれている。
私にとって、自転車は暴力的な乗り物になってしまったのだ。
その時に初めて私は失ったもの(お尻の贅肉)の大きさを知った。
悔しいが当時の私にとって、必要なのは自転車じゃなくてホントにエンシュアだったのかもしれない。
実体験だから正しいわけではない
そうなると、
早食いは太る・良く噛むと痩せる理論は間違いなの?
ってなるよね。
そうは言えない。
個人の実体験だけで結論を出してはいけない。
医療の世界ではご法度なんだ。
B型の特徴を色濃く持ってる私であっても、そこは躊躇しないといけないところだ。
主観まみれの感性は大事にしてるし好きだ。
ただ、同じくらいそのわきまえどきも大事にしないといけないって思ってる。
そんなアテにならない私の体験談に騙されないためにも、今日は噛むこととダイエット効果の関係について取り上げたいと思う。
③ダイエットの基本ルールは変わらない
体重の命運は”摂取”と”消費”の関係次第
まず外せない大前提は
体重は「摂取カロリー」と「消費カロリー」のせめぎ合いで決まる
ということなんだ。
体重の増減はどちらが優勢であるかの結果に過ぎない。
何をいまさら…って思わないでほしいんだ。
これ、ホント大事なんだ。
命運を分けるのは消費と摂取のバランス次第
消費する以上に食べれば太る。
食べる以上に消費すれば痩せる。
非常にシンプル。
……が故に残酷だ。
太るか痩せるかの命運は結局はこれに尽きてしまう。
どんなに私が「たくさん食べている」と駄々をこねても、私が痩せている以上は消費が多いか、摂取が少ないといった現実を突きつけられてしまう。
敵(看護師さん)に私の大事なお酒にエンシュアを入れる大義名分を与えてしまうことになってしまう……。
私は自身の体型から推察するに、油断すると摂取より消費がすぐに上回ってしまうのだろう。
言わばカロリーの浪費家。
貯めることを怠り、すぐ使ってしまう。
私の身体はお小遣いをすぐに使い切ってしまう小学校低学年のようだ。
きらきらしたダイエット法には注意?
全てを把握しているわけではないけど、目を惹く”楽して痩せるダイエット法”というのは基本的には穴があることが多いって私は感じている。
いつかは個別にも取り上げたいとは思ってる。
穴の例を少しあげると、短期的にみたら減量しやすくても、その反面、長期で見た際にリバウンドしやすかったりするっていうものがある。
また、短期で痩せるからこそ起こり得る別問題が隠れていたりもすることがある。
そのため、ダイエット・減量においての基本ルールは常に意識しておきたい。
【体重の命運を決めるのは、摂取カロリーと消費カロリーの差である】
これが不変の基本ルール。
……しつこいのは分かってるんだ。
でも、これがわからないまま「〇〇だけで痩せる!」に飛びついて、しょんぼりしてる人をたくさん見てきた。
だからこれだけは言わせて欲しいんだ。
たまには真面目な私もだしていきたい。
一見、変わったダイエット法に見えても、この基本ルールで大抵説明がつくと感じてる。
じゃあ、本題の“よく噛む”という行為。
これも基本ルールに照らし合わせて捉えることができるんだ。
じゃあ、この噛む行為は”摂取”と”消費”のどちらに影響してるのだろう?
④噛むだけで“攻め”と“守り”?──二刀流の実力とは
噛む行為は意外にも「摂取」と「消費」の両方に関わっている。
ちょっとだけ運動みたいな面もあるし、ちょっとだけブレーキの役割も果たす。
便利だけど地味で、地味だけど密かに効果が見込める。
私は人であっても、そういう縁の下の力持ちタイプが好き。
噛むっていうのは、そういう存在だ。
今日はその中の”噛むこと”と”消費”の関係について触れるね。
「噛むこと」自体が消費を増やしてくれる?
私たちの一日の消費エネルギーの内訳はざっと挙げると、こうなる↓
- 基礎代謝:約60%
- 食事誘発性熱産生(DIT):約10%
- 身体活動による消費:約30%
見ての通り、消費エネルギーの半分以上を占めるのは耳馴染みのある”基礎代謝“だ。
「基礎代謝を上げるためには筋肉をつけましょう」という話は、どこかで聞いたことがあるかもしれない。
筋トレ神話の一端だ。
ここでも筋肉は裏切らない……?
この話題も凄くとりあげたいところだけど、今回は”噛むこと”が主役だから我慢だ。
残念だが、筋肉にはいったん引っ込んでてもらう。
今回の主役は真ん中──「食事誘発性熱産生(DIT:Diet-induced thermogenesis)」だ。
⑤“食べるだけで燃える”ってどういうこと?
食事誘発性熱産生(DIT)……。
字面だけだとチャッカマンみたいだ。
これは食事を摂ること自体で、身体がカロリーを使ってしまう(熱産生する)、という摩訶不思議な現象。
蓄えるために摂取しているのに、摂取するには消費する必要がある。
これだけ聞くと本末転倒感がすごい。
そのアンビバレントさは魅力だ。
この矛盾溢れるDITは「よく噛む」ことで増える、という報告があるんだ。
噛む・食べる・そして燃える
早く食べる場合とゆっくり食べる場合を比較した研究があるんだ。(食事時間と噛む回数を記録)
それによると、ゆっくり時間をかけ、噛む回数の多かった方がDIT(食事誘発性熱産生)が高かったといった結果が実際にみられたらしい。
(参照:Yuka hamada,et al:The number of chews and meal duration affect diet-induced thermogenesis and splanchnic circulation:obesity,silver spring.2014 May;22(5):E62-9.doi)
口を動かすだけでカロリーってそんなに消費されるの?
って感じだけど、これには少し専門的な理由があるみたい。
その鍵を握るのが褐色脂肪細胞。
何か“焦げた霜降り”の情景が目に浮かんでしまう名前だ。
この焦げた霜降りはエネルギー消費を高め、体脂肪を減らす働きを待っている。
焦げた霜降り(褐色脂肪細胞)の逆襲
脂肪の名を語りながら脂肪を燃やす──そんな矛盾を抱えた褐色脂肪細胞。
汚名返上なのか、何かに目覚めたのか、過去に何があったのか……気になる存在だ。
真面目な話をすると、脂肪細胞にも種類がある。
一般的にイメージされるお肉を貯める憎きイメージの脂肪は”白色脂肪細胞”と呼ばれる。
変わり者の褐色脂肪細胞、別名”焦げた霜降り”は肥満予防や治療のターゲットとなりうる可能性が指摘されている。
(参照:Wouter D van Marken Lichtenbelt,et al:Cold-activated brown adipose tissue in healthy men.N Engl J Med. 2009)
この量が多かったり、活発であるほどに体脂肪率やBMIは低く、かつ代謝が高いといった傾向が認められたんだ。
頼もしすぎる。
焦げた霜降りは、いわばダイエット界のホープだ。
またこのホープは季節の好みもあるらしく、夏よりも冬の方がエネルギー消費が高くなるとも言われている。
(参照:Masayuki Saito et al:High incidence of metabolically active brown adipose tissue in healthy adult humans: effects of cold exposure and adiposity.Diabetes. 2009 Jul.)
ここは親近感を持てる。
私も夏か冬かと聞かれれば冬の方が好きだ。
冬は人肌恋しくなって寂しいから苦手?
私は独身だがそんな境地にない。
私にとっては人肌を感じたい寂しさより、高温多湿を感じないことの方が遥かに優先度が高い。
だから冬が待ち遠しい。
「噛む+たんぱく質=DIT アップ?──ご乱心の理由」
ちなみに、DIT(食事誘発性熱産生)は「何を食べるか」によっても差が出るって言われている。
その内訳はざっくり、こんな感じだ。
- 糖質:約6%
- 脂質:約4%
- たんぱく質:約30% ←ご乱心枠
──見ての通り、たんぱく質だけ妙に張り切っている。
摂ったカロリーのうち、3割近くを自ら燃やしてしまうなんて、どうかしてる。
ご乱心レベルだ。
エネルギーを得るために摂ったのに、その準備でエネルギーが消えるって、もう哲学か何かだ。
勉強するために散らかった机を片付けたのに、片づけた机を散らかしたくないから勉強を怠る私みたいだ。
ここで言いたいのは、同じカロリーを摂るなら、たんぱく質が多いほうが“燃費が悪い”ということになる。
燃費が悪い=たくさん消費してくれる。
つまり、それだけ「摂ったのに減ってる」という、ありがたい矛盾が生まれるわけだ。
よく「ダイエット中はたんぱく質を意識して」なんて言われるけど、こういう背景がある。
こうなると
じゃあ、ステーキを噛みまくって食べれば最強では?
と邪な発想が出てしまう。
そんな邪な発想をする私のような不届者がいた時のための基本ルールである。
散々、強調した理由がここにあるんだ。
基本ルール
【体重の命運は摂取カロリーと消費カロリーの差である】
そう。この基本ルールがある限り、いくら噛んで消費しようが、取り過ぎれば太る。
ステーキをいくら噛んでも食べ過ぎれば太り、顎が疲れるだけに終わってしまう。
よく噛むことは第一歩
ただし、噛むことで消費が増えるのは確かみたいなんだ。
食べ過ぎには敵わないが、太ることに対してささやかながらブレーキをかけてくれる存在であるに変わりない。
噛むことによるダイエットの貢献度の高さについてどう捉えるかは人それぞれだと思う。
今回は触れなかったけど、噛むことは”摂取”の部分でも太るのを防ぐ働きを持っている。
太る・痩せるといった体型のコントロールは言わば戦争みたいだ。
消費カロリーと摂取カロリーのせめぎ合いによって結果が左右される。
噛むことというのは一見地味で貢献度も低いように見える。
ただ、
戦争の素人は戦略を語り、プロは兵站(へいたん)(※2)を語る
(※2)兵站(=補給・支援体制)
っていう言葉もある。
個人的に噛むことは兵站の一部に位置すると言っても良いんじゃないかなって思ってる。
……それも、実は“前線”にも出てくる二刀流の兵站だ。摂取と消費、両方にじわじわ効いてくる。
何事も小さなことの積み重ねが大事。
噛むことに劇的な効果はないかもしれない。
でも、人生の変化って、だいたい“劇的じゃないこと”から始まるものだと思う。
冒頭で書いたように私は痩せの早食いだ。
普段、全然噛んでない可能性が多分にある。
そんな私だから、説得力はゼロになってしまうかもしれない。
でも、今回は私の早食い体験ではなく、信頼できる研究のお話だ。
私が噛まなくても痩せている点については……どうか、お目こぼしを。
痩せたいから噛む?──それとも、ちゃんと味わいたいから噛む?
私は両方とも足りていないようだ。良い子も悪い子にも真似は推奨できない。
ただ、その噛むという一口を大事にすることから、人生の”噛みごたえ”も変わってくる気がする。
私もできるところから頑張っていこうって思ってる。
⑥今日の小さな補足
噛む行為と交感神経
噛むという行為が交感神経を活性化させることによって褐色脂肪細胞による熱産生・エネルギー消費が高まるといわれている。
噛むことと摂取の関係
「早食いは太る」と言われるのは食欲調節との関係から指摘されている。
早く食べることにより食欲調節に関与する血糖値の上昇が起きる前、満腹感を感じる暇もない内にどんどん食べてエネルギーを過剰摂取してしまうといった問題からくるとされている。
白色脂肪細胞
過去ブログで小児期~青年期までにある程度、脂肪細胞の数が決まってしまうため子供時代の肥満にも注意が必要であるといった内容について触れたことがあります。この時の脂肪細胞が白色脂肪細胞になります。
過去記事は↓を参照
(参照:“ズルい”って思っちゃう身体の話──でもそれは“はじまり”の話)
参考文献
・Yuka hamada,et al:The number of chews and meal duration affect diet-induced thermogenesis and splanchnic circulation:obesity,silver spring.2014 May;22(5):E62-9.doi
・Wouter D van Marken Lichtenbelt,et al:Cold-activated brown adipose tissue in healthy men.N Engl J Med. 2009)