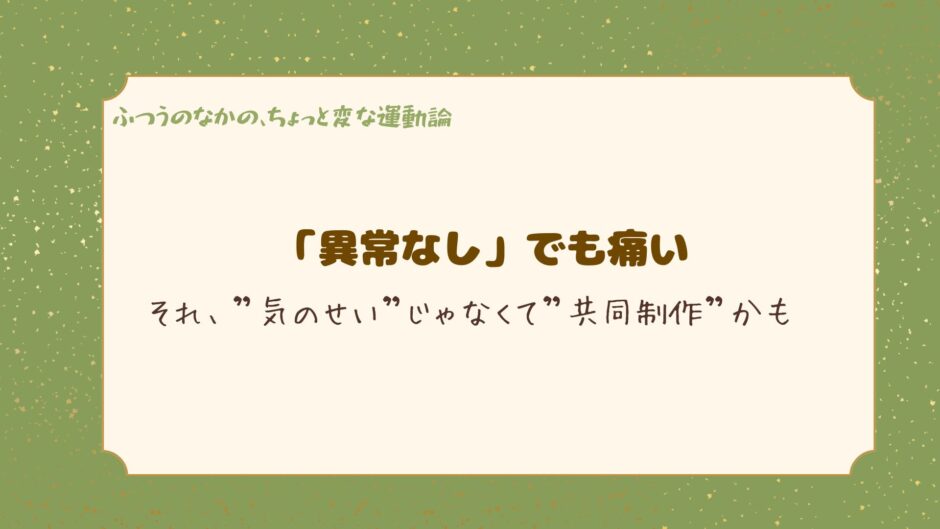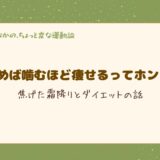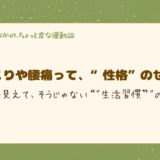「なんでこんなに痛いんだろう──病院でも“異常なし”って言われたのに……」
そんな経験、ありませんか?
目次
①”異常なし“でも痛い──”心と脳と身体の三人暮らし”が始まっているのかも
痛みのある人に「痛みは脳でつくられる」──なんて言ったら、怒られそう。
けど、それは一時テレビでも取り上げられて注目されたことでもあるんだ。
ただ、「痛みの“全て”が脳でつくられる」ってなると私も異議を唱えたくなる。
あくまでもひとつの要素であって、それで全て説明が付くとは思えないから。
「痛い、痛い……でも、腫れてないし、何もおかしくない」
そんなときに浮かぶ
「病院では異常なしって言われたのに何で?」
「気のせいなのかな?」
っていうモヤモヤに、今日はちょっと触れたい。
そもそも痛みって、本当に“そこ”だけの問題じゃなかったりもする。
“異常なし”なのに、なぜこんなに痛い?
それ、気のせいじゃなくて“共同制作”かもしれません。
心が痛みをこじらせる?
“心”が痛みを悪化させることがある──そんなことを言うと「気のせいってこと!?」と誤解されがちだけど、そうじゃない。
たとえば カタストロファイジング(Catastrophizing) という現象がある。
ものすごく悲観的になっちゃうことを指す専門用語。
「このまま一生治らないんじゃ…」「もう何もかもダメかも」といった痛みに対して、極端にネガティブになってしまう思考。
ネガティブや不安自体が悪いわけでじゃないんだけどね。
ただ、カタストロファイジングのような”不安の暴走”レベルになると要注意って感じ。
事実、このカタストロファイジングが腰痛などの慢性疼痛を長引かせる原因のひとつになることが、ガチで言われてたりする。
(参照:Maria M Wertli et al. Influence of catastrophizing on treatment outcome in patients with nonspecific low back pain: a systematic review.Spine (Phila Pa 1976). 2014.)
つまり、同じような痛みの原因であっても、その人の“心の温度”次第で、痛みの感じ方が変わるってことが確認されている。
「病は気から」なんて言葉、なんだか昭和的で私はアレルギー反応がでそうだけど、現代医学的にもあながち間違いじゃなかったりもする。
……だから今さらだけど、ちょっとだけ先人に敬意を表したくなったりする。
ゆとりは根性論が苦手(でも根性は大事だと思ってる)
私は「気合で治せ」とか「気の持ちよう」とか、そういう根性”論”には懐疑的。
ただ、根性や気の持ちよう自体はすごく大事だと思ってる。
あくまでも、その人の環境や個性を無視した力技だけの根性論が苦手なだけ。
パワー系根性論アレルギーな私。
私は世代的にドンピシャで
「ゆとり世代だからね〜」
ってよく言われた。
いやいや、こっちは望んでゆとってたわけじゃないし。
ゆとった覚えもない。
勝手にゆとらされて、勝手に叩かれて、何だそれは?
っていうのは私世代のあるあるムーブメントかもしれない。
そんな”ゆとり世代”の私であっても、【気の持ちよう】が大事になる場面ってやっぱりあるなって感じる瞬間がある。
心だけじゃなくて脳も大事
今日はそんな“心”の話だけじゃなくて、もう一つ書きたいことがあるんだ。
”もう一人のルームメイト”である、脳の話。
実は、痛みと脳の関係もめちゃくちゃ濃いんです。
②脳は、心の失恋にも、足の小指にも反応する
2%の重み
学生時代に解剖学実習で“本物の脳”を手にしたことがあるんだけど、あれは本当に衝撃だった。
テレビで見るような、あのシワくちゃの形のまんまで、手に持つとずっしり重い。
大人の脳の重さは1.2〜1.6kg程度、体重の約2%って言われている。
いや、ホンマにその程度?ってくらいに実際の脳は重たく感じた。
でもその2%が、私たちの司令塔的な存在になってるんだから、なんだか尊い。
私の脳もちゃんとそれだけ重くて、シワもあるはず。
でも、そんな尊い2%がバグると、いろいろ巻き添えを食らう。
恋による痛みも、タンスによる痛みも同じ?
たとえば、ある研究では、「心が傷ついたとき」と「身体が痛いとき」は脳の同じ場所が反応してたってことが報告されている。
(参照:Naomi I Eisenberger et al.Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. Science. 2003.)
つまり、
仲間外れにされたとか、恋人にフラれたとか、そういう「心の痛み」が、まるで足の小指をタンスの角にぶつけたような反応を脳に引き起こしてるってことだ。
失恋の痛みもぶつけた小指の痛みも同じように解釈するなんて、脳は賢いのか大雑把なのかよくわからない。
タンスにぶつけた痛みと失恋の痛み、どっちが痛いんだろう?
私の感性とは関係なく、脳にとっては【同じ痛み】らしい。
③痛みが続くと、決断力もやられる
また別の研究では、慢性的な痛みを抱える人は、“感情をともなう判断”が苦手になる傾向があるらしい。
注意力や短期記憶、一般知能とかの認知機能には差がなかったのに。
(参照:A Vania Apkarian et al. .Chronic pain patients are impaired on an emotional decision-making task.Pain. 2004 Mar.)
痛い時の決断には注意?
つまり、
- 結婚するかどうか
- 上司に言い返すかどうか
- サブスクの解約をするかどうか(←意外と重い)
身体に痛みがあると、そういう場面で、うまく決められなくなるかもしれない。
感情が混じった決断をするシーンでは、痛みが“判断のノイズ”になり得るってことだ。
痛みは性格を変える?
私の仕事柄、何かしらの痛みを抱えている人と毎日関わる。
そんな日々の経験から、これは少し腑に落ちる話だったりする。
痛みを抱えている人と関わる中で、時に冷静な判断や柔軟な考えが欠けているように感じることがある。
臨床現場に出たばかりの頃は、単純に「その人の性格かな?」くらいに思ってた。
でも経験を重ねるうちに、症状がよくなるとともに、思考の柔軟性がでてきている(戻っている)と感じる場面に何度も遭遇した。
持続する痛みは人を変える魔力がある。
ちなみに私は痛くなくても、感情を伴う意思決定の時はノイズだらけになりやすい。
そんな私にノイズが加わると……泥酔状態?
というのは冗談だけど、【痛みが人を変える】っていうのは自分に置き換えてもわかる気がする。
そもそも、痛いのは大嫌い。
私も少し続く身体の痛みを抱えたことがあって、そういう時に内省してみたけど、自分のメンタルがブレてるって実感したことがある。
何か意味もなくにイライラしたり、柄にもなく悲観的になったりと。
後になってみたら、何であんな風に考えていたんだろう?って。
そんな実体験からも【痛みを抱えている状態】っていうのは、人間関係や仕事のパフォーマンスとかに物理的な制約以上に凄く影響がでるって感じてる。
まさに、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の低下だ。
それはマズイって思ったのもあって、痛くならないように身体のメンテナンスには私は日々、自分なりの全力を尽くしてる。
④放っておくと、脳が“物理的に”変わってしまう
ここからちょっとホラー。
慢性痛が続くと、脳の“痛み関連領域”が過敏になるだけじゃなくて、
脳そのものが萎縮していく可能性があるらしい。
慢性腰痛の人は脳の体積が少ない…
たとえば、慢性腰痛をもつ人は、そうでない人と比べて 灰白質(※1)の体積が5〜11%も少ない という報告がある。
(※1)神経細胞の細胞体が集まっている部分。
(参照:A Vania Apkarian et al. Chronic back pain is associated with decreased prefrontal and thalamic gray matter density J Neurosci. 2004.)
「5〜11%くらいなら誤差じゃない?」って思うかもしれないけど、それ、老化でいうと10〜20年分の縮みなんだって。
お、恐ろしい。
そんな二桁単位の老け具合なんて考えただけでホラーだ。
痛みの期間と脳の体積の関係
この脳の体積の減少は痛みの続く期間と関連してるらしい。
具体的には痛みが1年続くにつれて、1.3㎤失われるとのこと。
1.3㎤は約小さじ¼杯分になる。
痛みを抱えていると、毎年それだけの量の脳が減っていくとか、地味に怖くない?
⑤でも、脳は戻るらしい(脳、えらい)
ここでちゃんと補足したいことがある。
恐ろしやって感じだけど、実は希望もちゃんとあるってことを。
痛みの問題が解決すれば脳は復活する?
これまた別の研究だけど、股関節の手術を受けた患者を対象にしたもの。
手術前は持続する痛みのせいで減っていた脳の“視床”(※2)の体積が、手術後9ヶ月で回復していたっていう報告があるんだ。
(※2)脳の部位の一つ。感覚情報を伝える中継基地のような存在。
(参照:Stephen E Gwilym et al. Thalamic atrophy associated with painful osteoarthritis of the hip is reversible after arthroplasty: a longitudinal voxel-based morphometric studyArthritis Rheum. 2010 Oct.)
つまり、痛い状態が続けば脳は萎縮するけど、痛くない状態に戻れば、脳はちゃんと元のかたちに戻るらしい。
脳の奇跡の回復力
脳ってそんなに変幻自在なのかって感じだけど、そうみたい。
毎年小さじ¼杯分とられたものを、しっかり奪い返してきてくれる。
──脳はちゃんとわかってる。
痛みのない日々が戻ってきたら、自分の形を取り戻してくれる。
奇跡のような回復力を発揮してくれる。
えらい。脳、頼もしすぎる。
⑥痛みは、身体と心と脳の三人暮らし
痛みのせいで脳が萎縮するっていうちょっとホラーな話をしたけど、痛みとの【向き合い方】ってホント大事なんだ。
痛みの原因は身体の問題だけじゃない
痛みって、「身体」だけじゃなくて、「心」や「脳」との共同制作みたいなもの。
同じ身体の痛みでも、
- 心がしんどいときは、余計に身体が痛く感じたり
- 脳がバグっていても、何の問題のない身体が痛くなったり
- 身体の痛みが続くと心が荒んだり、脳が萎縮したり
そんなふうに、三者が絶妙に絡み合って、「痛み」ってものをつくりあげている。
そんな痛みの共同制作を勝手に始める”いらんことしい達”を全力で邪魔するのが、私のお仕事。
三者の共同制作だからこそ、痛みには薬物療法や運動療法だけじゃなく、心理療法が有効となるケースもある。
脳のリハビリも必要?
場合によっては”脳”の機能に着目したリハビリも必要になってくるケースもある。
というのも、慢性腰痛を抱えている人は、同じ刺激に対しての反応が痛みのない人と異なってることが指摘されていたりもする。
(参照:Thorsten Giesecke et al.Evidence of augmented central pain processing in idiopathic chronic low back pain.Arthritis Rheum. 2004 Feb.)
つまりは、慢性的に痛みを抱えている人はそうでない人と比べると、脳機能そのものが異なっているといった一面もあるみたい。
神の手は存在しない?自助努力の重要性。
持続する痛みには、一面的でなく多面的に捉える柔軟性が大事になってくる。
これは、何も治療を提供する側に限らない話だと思ってる。
それどころか、実際に痛みの渦中にいる本人の方が、より大事になってくると私は感じている。
私のような仕事は、見方によってはあくまでもサポートに過ぎなかったりする。
悔しいけど、医療提供者側の力だけではとてもじゃないけど対処できないケースは沢山ある。
本人の努力や協力なくして解決しないことって沢山ある。
どんな痛みも瞬時に治す「神の手」なんて、存在しない。病態によって“そう見えること”はあっても、それだけでは解決しないことも多い。
その反対で、明らかに回復が異常に早い人もいる。
このケガや病態なのに何でそんなスピードで痛みがなくなっていくの?って。
痛みにも機嫌がある
また、痛みにもバイオリズムがあったりする。
特に理由はないのに調子が良かったり、悪かったりする。
朝起きた瞬間に気分が晴れてる時もあれば、理由なく曇ってる時があるように。
痛みに対しては時に鈍感力も大事
痛みは、体と心と脳の三人暮らし。
そして、その三者も日によって機嫌が違う。バイオリズムだってある。
そんな日は、無理に原因を探さず、「まあ、今日はそういう日か」と思う鈍感さも時に大事。
それは無関心ではなく、やさしい共存の仕方だったりもする。
⑦今日のちょっとした補足
参考文献
・Maria M Wertli et al. Influence of catastrophizing on treatment outcome in patients with nonspecific low back pain: a systematic review.Spine (Phila Pa 1976). 2014.
・Naomi I Eisenberger et al.Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. Science. 2003.
・A Vania Apkarian et al. .Chronic pain patients are impaired on an emotional decision-making task.Pain. 2004 Mar.
・Stephen E Gwilym et al. Thalamic atrophy associated with painful osteoarthritis of the hip is reversible after arthroplasty: a longitudinal voxel-based morphometric studyArthritis Rheum. 2010 Oct.
・Thorsten Giesecke et al.Evidence of augmented central pain processing in idiopathic chronic low back pain.Arthritis Rheum. 2004 Feb.